
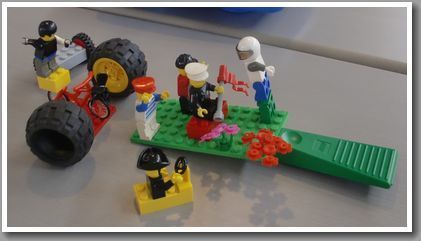
このたびは「木下耕二 ラーニングコラム」にお越しいただき、ありがとうございま
す。経営コンサルタント(重点ドメイン;人材育成コンサルタント)の木下です。私
は、清涼飲料メーカーでの勤務経験を経た後、日本生産性本部の専属経営コンサ
ルタントとして2000年から、中堅・中小企業を中心に、経営戦略、CS・マーケティ
ング、業務改善、能力開発など幅広い視点から顧客と共に競争優位性、収益性の
アップ・財務状況の改善に邁進してきました。僭越ながら、省察的・学術的実践家を標榜しています。まだまだ道半ばです。
私は経営コンサルタントとしてのキャリアを積んでいく過程で、『組織の人材育成は経営※に役立つべき(資するべき)』と強く考えるようになりました。
※経営:収益状況や財政状態の改善、シェアアップ、競争優位性の強化、さらなる独自性の向上等
組織の人材育成は当該組織の経営、事業運営に役立つべき(資するべき)。経営に、事業運営に貢献しない組織の人材育成はありえない。考えとしてはOK。当然。しかし、お分かりのお方はお分かりかと存じますが、この当然のことが、多くの組織で実現できていない。いやできない。
当然のことが実現できない現実は、経営コンサルタントである私にとっては大問題でした。競争優位性、収益性のアップ・財務状況の改善を目指す経営コンサルティングにおいて、相応の予算を使って実施する人材育成施策が、「経営に役立って(経営に資して)いない=競争優位性、収益性のアップ・財務状況の改善等に寄与していない」のですから。
私は経営に役立つ(資する)人材育成施策の立案・実践を目指し、人材育成施策の上流工程から下流工程まで、幅広く、積極的に関与するように努めました。
【人材育成施策の構築・実施のプロセス】
経営(事業運営)の目的・目標、戦略・戦術の理解・納得 ⇒ 最も重要!
↓ ↑
経営(事業運営)と人材育成施策の関連付け、リンケージ
人材育成施策の限界の見極め
↓ ↑
経営(事業運営)に資する人材育成施策の目的・目標の明確化
↓ ↑
人材育成予算額の検討・決定
↓ ↑
人材育成体系の構築
↓ ↑
人材育成施策と他の経営施策との連動(相乗効果の発揮)の検討
↓ ↑
人材育成施策の検討・企画
↓ ↑
人材育成施策の実施
他の経営施策の実施
↓ ↑
効果の測定・評価、実施施策の振り返り
↓ ↑
実践性、効果性、効率性を増した研修の実施
↓ ↑
以上の繰り返し、スパイラルアップ
人材育成施策を
『検討・企画する立ち位置から見る景色・想い・感情』と、
『実践する位置から見る景色・想い・感情』、例えば、具体的な成果の実現を早期に期待されている
状況下でその実力がない方の育成をミッションとして与えられている時の景色・想い・感情、研修が
始まる前から研修の開催に疑念や反感を有する受講者と正面から対峙する際の景色・想い・感情
は、明らかに違います。
私は、人材育成施策を、『実践する位置から見る景色・想い・感情』を存分に見る・感じるために、
いままで以上に実際にOJTTしたり、研修講師としてより積極的に登壇したりすることに務めまし
た(現在も務めています)。このようなことに務めながら、『経営(事業運営)に役立つ・資する人材育成を!』との強い思いを
抱き、経営コンサルティング、人材育成という二足のわらじを履いて仕事を続けてきました。
そして、あらためて気づきました。
『経営コンサルティングと人材育成、どちらの仕事も、そのフィールドは、とてつもなく広く、深い』
『人材コンサルタントとして 一流を目指し、お客様の期待を満たす・超えるためには、経営コンサル
ティング、人材育成、どちらかの仕事に優先して取り組まねばならに。そうしないと一生でも時間が
まったく足りない!』人材育成の仕事を経営コンサルティングの仕事に優先させることとしました。
人材育成の仕事を優先させることとした理由には、上記の他に以下のようなものがあります。
●「人材を育成すれば業績が向上するなど経営に役立つ」とは必ずしも言えない。しかし、(あくまで
個人の経験と勘に基づくものではあるが、)「人材育成が業績向上など経営に役立つケースは多
い」「特に中長期的には」と自信をもって言える。
●人材育成のフィールドの方が経営コンサルティングのフィールドより狭い。
●人材育成において成果を期待される期間の方が、経営コンサルティングにおいて成果を期待され
る期間よりも、より中長期であることが多い(じっくり腰を落ち着けて取り組める)。
↓
●人材育成は経営コンサルティングよりも、スペシャリティを、多少は、高めやすい(のではないか)。
↓
●お客様のお役に立てる可能性がより高い(のではないか)。
●人の成長に強い喜びを感じる。
●人材育成の方が経営コンサルティングよりも、私のパーソナリティ、特性を、おそらくより活かせる
(のではないか)。
経営コンサルタントとしての経験・知見を有効活用しながら、人材育成のスペシャリティを高め、組
織・企業に真に役立てる人材育成コンサルタントになろう。クライアントの有能なサポーター足るべく
精進しよう。2008年。そう決めました。
人材コンサルタントの道を優先すること決意して以降、私は人材育成体系の検討、個別研修プロ
グラムの企画、研修講師としての登壇等に、それまでにも増して力を注ぎました。
人材育成の実践に係る経験の量の増大を図りながら、同時に、人材育成に関する理論の学習・
理解に以前にも増して没頭しました。理論によって人材育成に関する知識の枠組みを構築し、「人材育成に係る具体的な経験を理解・
整理するための知識体系の受け皿を作る」。そして「知識体系の受け皿に具体的な経験をどんどん
盛る」。これを繰り返すという戦略です。
経営コンサルタントとしての仕事は、経営の現実を”(頭ではなく)体”で感じる上で、極めて重要な
場と捉えています。『経営コンサルタントの仕事は、私の人材育成の仕事を下支えする』と私は認識
しています。私は、現実の経営課題(業績の改善や中期経営計画の立案・達成、実践等)を”教材”に、お客様
と結成したプロジェクトチームにおいて、お客様と一緒に現実の経営課題にぶつかっていくというス
タイルで仕事をすることが多いように思います。その過程で幹部やリーダーを見出し、また彼らの能
力開発をご支援させていただいています。
このような人材育成のやり方(取り組み)に私が違和感や怖れを抱かないのは、いえむしろ歓迎
するのは、経営コンサルタントとしての仕事のやり方が、私の仕事のやり方のベースとなっているか
らかと思います。また、現実の課題が最上の教材であると信じているからです。私は、経営コンサルタントとしての実践の経験を起点・ベースとしながら、人材育成コンサルタント
してのキャリアの道を今後歩んでいきたいと考えています。
「うまくいった」と自己評価できる人材育成もありますし、「もっとこうすればよかった」「あの打ち手
とあの打ち手の順序は逆であった」などと反省する人材育成もあります。経営・組織の論理を優先するか、個としての人の論理を優先するか。
「経営に役立つ(資する)人材育成を!」はいいが、そもそも経営の方向性が定まらない。どうする
か・・・。人の育成よりも事業からの撤退を選択すべきではないか・・・。
悩みは尽きません。
経営に役立つ(資する)人材育成を! との強い思いを胸に、個々の組織・企業にフィットする有益
な人材育成サービスを提供することを目指し、精進し続ける所存です。
2011年10月 8日
2013年 1月20日 改訂
2013年 8月 3日 改訂
木下耕二

